「よーし美桜、次はシュークリー…………」
「日和、限界! もう食べられない」
六個めのケーキを完食し、美桜は後ろに倒れ込んだ。
普段からそんなに食べる方ではなさそうなので六個でも頑張ったのだと思うけど、机の上には美桜が食べた数と同数のケーキがまだ残っている。
「六個かー。美桜、まだまだケーキバイキング、余ってるよ」
「日和、悪意がある。そんなに食べられないって。でもすっごく美味しかった! ケーキ食べたのいつぶりだろう。今まで食べた中で一番美味しかったよ!」
美桜をうちに連れてきたら、数年ぶりに私が友達を連れてきたことにお母さんのテンションが上がってしまい「おやつだよー」と、別々の種類のケーキを十二個持ってきた。
昔は友達が来ると、ケーキをおやつに出してくれるのが定番だったので想定通りだったけど、そんなに持ってくるとは思わなかったので、お母さんも感覚がおかしくなってるんだろう。
でも、そんな感じになってしまうほど、友達を家に連れてくることがなかったという事実に、申し訳なさからちょっと凹んだ。
(いかんいかん、そんなこと考えてる場合じゃない)
お母さんが持ってきたケーキは、単純計算で一人六個の計算だけど、イタズラ心で「全部美桜のぶんだよー」と言って、ケーキバイキングにしてしまう。
普通の女の子がどの位ケーキ食べるのか知らないけど、美桜はショートケーキ、チーズケーキ、モンブラン、フルーツタルト、ティラミス、レアチーズケーキと、私がおすすめするのをどれも「美味しい!」を連発して食べてくれた。
お父さんの作るケーキは私もすっごく好きなので、それを褒めてくれてるのは私も嬉しかった。
美桜、えらいぞ!
「当分、ケーキ、というか甘いものいらない」
「ごめんごめん。うちのお母さん、久しぶりに友達連れてきたから張り切っちゃったみたい。残りどうする? 持って帰るなら包んでくるけど…………でも、美桜はあまりお土産とか持って帰りたくないか」
「……………………」
すぐに肯定する返事がくると想定していたけど、美桜は何かを考えている様子。
「美桜?」
「あ、うん、ごめん。あの、もしよかったら包んでもらってもいい? 母親と父親が食べるかわからないけど、私が食べる。てか、食べたい! 図々しくてごめんね」
「あれー美桜ちゃん、当分甘いものいらないんじゃ?」
美桜はあわてた様子で何か喋ろうとしているが、声が出ていない様子が面白くて、クスッと笑ってしまう。
「ごめんごめん、冗談だよ。それじゃー包んで来るから、お茶でも飲んでゆっくりしてて」
「…………ありがと」
倉庫からケーキを入れる箱と手提げタイプのビニール袋を持ってきて、台所でケーキを包装する。
このケーキは誰が食べるのだろうと想像しながら…………。
美桜に食べてほしいけど、会ったこともない美桜のお父さん、お母さんでもいい。
私は、お菓子は人を幸せにすると信じている。
ふと、気配がして振り向くと、弟の|優《ゆう》が立っていた。
「なんだ優か。いたんだ。今、私の友達が来てるから、もし会ったら挨拶してね」
「母さんから聞いた。『あの子がお姉ちゃんの好きな子なのかな』って、ゴキゲンで言ってたよ」
「な、な…………、なに言ってんのよ」
「その様子じゃ、アタリかぁ」
てっきり、からかわれると思って身構えていらた、優はバツの悪そうな顔をして、頭を掻いている。
「そっかー。いや、姉ちゃんごめん。俺が母さんに姉ちゃんの好きな奴は同じ高校とか言っちゃったから、母さんも完全にそう思ってるみたいで…………。デリカシーってのがなかったわ。ごめん」
「な、なに言ってんのよ。そもそも、私が美桜のことが好きだって言ってないし」
強がってはみたけれど、私にとって美桜が普通の友達ではないことを、私が私の態度で証明してしまっている。
ここからどう弁明すれば良いのか分からないし、そもそも優は私の嘘などには引っかからないだろう。
「うーん。まぁ、そうだよな。姉ちゃんがそう言うなら、それでいいよ。母さんにも何か聞かれたら適当に答えとく。でも、姉ちゃんが、そのミオさん? って人のことを、友達と思ってても、好きな人だと思ってても、付き合ってても、俺は別にどうも思わないから。姉ちゃんの思うようにしなよ。応援してるわ」
こんなことを言われたら『気持ちわるいヤツ』とか思うかもしれないけど、優が言うと、なんだから変な納得感と自信をもらえた気持ちになるから不思議だ。
「はいはい。ありがと」
私は変に照れ臭くなってしまい、適当な相槌を打つと、優は満足したのか、靴を履いてどこかへと出かけていった。
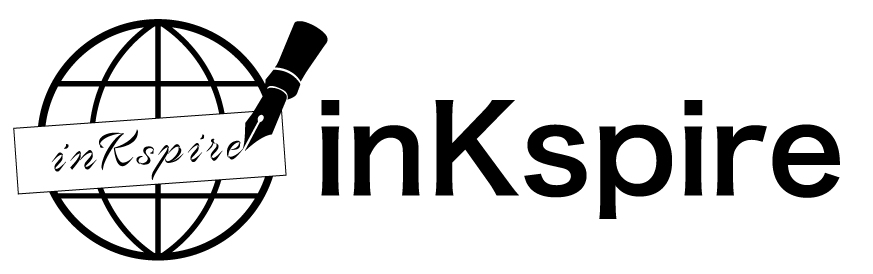




コメント