(なんだ、なんだ、なんだ、なんだ!)
「かわいすぎるだろーーーーー!」
以前、美桜に敵意を向けられて酷い言葉を投げかけられていた時。
私はそれにウンザリしつつも…………、鬱陶しいと思いつつも…………、そんなことをする理由が理不尽なものだったらやっつけてしまおうかと思いつつも…………、どこかで『美桜の笑顔が見たい』と思っていた。
そしてその後、奇跡的に友達になれた時。
美桜の泣いた顔、そして笑った顔をたくさん、たくさん見ることができた。
それで十分だと思っていた。それが全てだと思っていた。
「全然違うじゃん!」
今日は普通の日だったはず。
なんの変哲もない、普通の日だったはず。
とくに予定もなかったので、いつも通り図書室に来て、いつも通り美桜の隣に座って、いつも通り本を読んで、あとはいつも通り帰るだけだった…………はず。
別に、さっきの美桜だって特別なことをした訳じゃない。
私にちょっとしたイジワルをしたかっただけだろう。
ただ私は、まったく反応できなかった。
『美人』って言われたから? 『かわいい』って言われたから? 多分違う。あの少し澄ましたドヤ顔は、昔も見たことがある。
あれは、まだ友達になる前、精一杯の美桜の強がりだったと思う。
あの時と同じだったはず。違うのは、私と美桜が友達同士になったという関係だけ。
けれど、友達として一緒の時間を過ごしているだけで。
何をするわけでもない、何かをされるわけでもない。
図書室の隣の席で一緒の時間を過ごし、たまに公園で少し話をするだけ…………たった、それだけで。
「これ、絶対ダメなやつだ。|優《ゆう》が言った通りだ」
一人、トイレの鏡の前で、自分の中に溜め込むことができなくなった気持ちが、自然と言葉としてこぼれる。
「私、美桜のこと、好きだ」
私の弟の優は、相手の笑顔が見たいという気持ちを抱く理由として「相手のことが好きなんじゃない?」と言った。
そのときは『そんなこともあるのかな』くらいに思っていた。
けれど…………もう認める、認めるしかない。
美桜が女の子だからとか、関係ない。
今までも、美桜に対して、単なる友達とは違う、特別な感情を持っていることに気づいていた。
ただ、今日、さっき、美桜とした何気ない会話で確信に変わった。
私は…………私が…………初めて好きになった人が、『風間 美桜』という一人の女の子だったというだけ…………たったそれだけのこと。
「……………………」
「ふーー――。さてさて」
大きく息を吐き、顔をあげる。
目の前の鏡には、顔を真っ赤にしながらも口元の緩んだ自分が映っている。私が知らない私がそこにいた。
(私、こんな顔できるんだ)
今この瞬間に認めた自分の気持ちがストレートに顔に出ている。
「不変なものはない……か。うん。確かに、確かに!」
「ヨシ!」
あまり美桜を待たせても悪い。
いつもどんな顔をして美桜に接していたかも思い出せない。
であれば、もう行くしかない。
「ヨーシ。やるぞー!」
鏡の中にいる自分に向けて、グッとファイティングポーズをとったあと、握りしめた右手を前に突き出す。
鏡の中で左手を突き出す自分が、何だか勇ましい感じで嬉しくなった。
「お、お待たせー」
「大丈夫? ちょっと顔赤いけど、熱とかない?」
「だ、大丈夫、大丈夫。ちょっと図書室暑かったからかな。全然平気。元気元気!」
「ならいいけど」
文化系の部活の生徒は帰ってしまったのか、校舎内に人影はなく、蛍光灯が寂しく廊下を照らしている。
ちょっと怖いので、一人だったら玄関まで走っていったと思うけど、美桜がいるからか、不思議と怖いという気持ちはなかった。
それに、先ほどまであんな顔をしていた自分を他人に見せたくない。
「うー。寒い」
玄関から外に出ると一気に寒さが増す。美桜は腕を抱えて縮こまっていた。
「美桜、私、自転車とってくるから、ここで待ってて」
「あ、私も行くよ」
「…………ありがと」
自転車置き場にも人の気配はなく、残っている自転車も数台程度。
辺りも薄暗く、美桜が付いてきてくれて助かった。
「あ、美桜、後ろ、乗ってく?」
「え、二人乗り、見つかったらまずいんじゃない?」
「もう下校時間かなり過ぎてるし、大丈夫だよ。それに、美桜の家近いし」
私のせいで遅くなってしまったのでそう提案したけど、美桜はあまり自分の家が好きじゃないので、もしかしたら早く帰りたくないかもしれない。
少し後悔しながら美桜の方を向くと、美桜は何かを言いたそうな顔をしていた。
「美桜、どうしたの?」
「やめとく。自転車の後ろ、乗ったことないから。暗いし、危ないし、今度練習しておくから、そしたら乗せて」
本当にバツが悪いという顔をしているので、思わず吹き出して笑ってしまった。
「な、なに笑ってるのよ! そんなにかっこ悪いかなぁ。でも、慣れてない人を乗せて、転んで日和に怪我させても悪いと思うし」
「ふふふ……、いや、ごめんごめん。全然大丈夫、かっこ悪いとか思ってないよ」
「うそ。じゃあなんで」
(これは、ちょっと本気で怒っているかな)
ちゃんと言葉を選んで説明する必要を感じた。
「ごめん。美桜のこと、かっこ悪いとかそんなこと思ってないよ。これは本当。いや、よく考えたら、私も二人乗りなんかしたことなくて、当然後ろに乗ったこともなくってさ」
「だったら何で提案したの?」
「帰る時、私がトイレに寄ったせいで遅くなっちゃったからだけど、でもそんなことはどうでも良くて、笑ったのは、美桜が「後ろに乗る練習する」って言ったから…………面白くって」
「面白い? だって、やったことないんだから、練習するしかないじゃない」
「えっと、美桜、気づいてる? 二人乗りの後ろの乗る練習ってことは、誰かが前に乗って自転車を漕がなきゃいけないんだよ? 一人じゃ練習、できないんだよ?」
「………………」
美桜は、私が笑った意味がわかったのか、赤面し、声にならない声を発している。
そんな美桜をみて、愛おしいと感じていたけど、もし、自転車の二人乗りを練習するのなら、自転車を漕ぐ役目は、私がやりたい。
(ちひろじゃなくて…………)
「美桜ちゃん。練習するなら日和お姉さんも誘うんだよ。美桜ちゃんの壊れた自転車じゃ練習できないし、日和お姉さんも、美桜ちゃんを後ろに乗せて自転車を漕ぐ練習するからね」
両手を後ろで組み、小さい子に諭すように、美桜の顔を覗き込みながら私の希望を伝える。
ついでに頭も撫でであげようとしたら、流石にそれは許されなかったみたいで、美桜は私の手の届かない位置まで後ろに下がるとプイッと横を向き「……バカ」と、小さく口にした。
「ふふ、さてさて、二人乗りの練習はいつかにとっておくとして、そろそろ本当に帰ろうか」
「まったく、まったく日和は……」
美桜は何か言いたそうだけど、何を言っても自分に分が悪いと思ったのか、黙って横を歩いている。
以前、同じように何も話すこともなく並んで歩いたときは、お互い気まずくて仕方なかったが、今はそんなことはなく、むしろ心地いいとさえ思う。
こんな日が続くといい。
「あー、日和が変なこと言うから、忘れるところだった」
急に美桜が大きな声を出した。
「いきなり大きな声出さないでよ。びっくりするじゃん」
「いいの! あのさ日和、駅の近くで毎年イルミネーションやってるじゃない? それ、見に行かない? ちひろも誘ったんだけど、大丈夫って言ってたから三人で。あ、でも、予定あるんだったら断ってくれていいから。うん。全然大丈夫」
「……………………」
「日和? どうかな…………。ダメ?」
ダメじゃない。
美桜から遊びに誘ってくれたのは、めちゃくちゃ嬉しい。ただ、自分の気持ちがはっきりしてしまったせいか、『三人で』ということに変に引っかかってしまった。
自分でもこんな気持ちになるなんて想像もしていなかった。
「ああ、うん。いいよ。いいね。楽しみしてる!」
自分でもちょっと微妙な返事になってしまったと分かる。
美桜に変に思われていないだろうか……。
「わかった。ありがと。イルミネーション始まらないと意味ないから、始まったらその週末に行こうか。ちひろにもそう伝えておくね」
「うん。よろしく」
「それじゃー、私こっちだから、付き合わせちゃってごめん。ありがとう。ばいばい!」
「うん…………」
美桜は、嬉しそうに笑って帰っていった。
私の動揺は伝わらなかったみたいで安心する。
もしかしたら、美桜は初めて友達を遊びに誘ったのかもしれない。
それが私だったら嬉しかったけれど『ちひろも誘ったんだけど、大丈夫って言ってた』ということは、ちひろにはもう話した後なのだろう。
それがすごくモヤモヤする。
「ただいまー」
「お、姉ちゃんおかえりー。何だかテンション低いじゃん。どうした? 好きなヤツにフラれた?」
お風呂上がりなのか、濡れた頭のまま弟の|優《ゆう》が出迎えられた。
「何言ってんのよ。バカ。女子高生には色々あるの」
「だよなー。逆に色々なかったら、何で女子高生やってるのか分からないもんなー。何かあるからこその女子高生。で、告ったの?」
「何で色恋沙汰限定の『色々』なのよ。お前の頭の中は真っピンクか! もう少し違うことに頭使わないと、バカになるよ。バカに」
「ならんわ! こう見えて成績は良い方なんで! ま、また進展あったら教えてくれぃ」
よっぽど良いことがあったのか、私に対してマウントを取りたいのか、はたまた単なるバカなのかは分からないけど、テンションの高い優は、笑いながら自分の部屋に行ってしまった。
(なんだあいつ。…………でも、ちょと聞きたいことあったんだけどなぁ)
「あ、日和おかえり! お母さんとお父さん、さっき急なケーキの注文が入っちゃってお店の片付けが遅れてるの。ご飯もう少し先だから、お風呂入っちゃって」
「ほーい」
(まぁ、また今度でいっか)
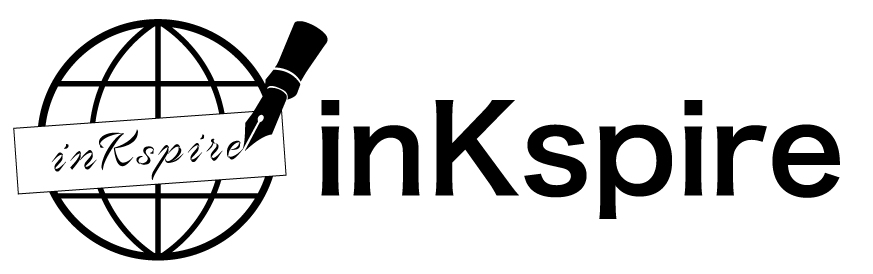




コメント