私はなんなのだろう。
青井 日和が嫌いだった。
ただそれは、嫌うことで自分の精神を安定させていただけだった。
自分が正しいのだと。
こんな私には絶対にならないはずだった。
私は、親にも迷惑をかけることが少ない手のかからない子供だったと思う。
必死に努力した結果だけど勉強もできたし、昔は今よりも友達も多かった。
ただ、私は何をしたかったのだろう。
私の意思はそこにあったのだろうか。
子供の頃の思い出は正直に言ってあまり良いものがない。
悪い思い出が多いのではなく、何か心に残っていることとか、そういうものが無いのだ。
笑っていたこともあったと思う。
ただそれ以上に思い出されるのは『悔しい』と感じたこと。
『苦しい』と感じたこと。
『嫌だ』と感じたこと。
そして『何でそうなるの?』と納得がいかないことばかりだった。
父は普通のサラリーマン、母親は専業主婦、子供は私1人。
家族構成はいたって普通だと思う。
父親は一人娘に対して溺愛するような人ではなく、むしろ放任主義で、必要以上に話をする性格でもない。
正直、何を考えているのか、今になってもわからない。
母親は短大を卒業後、父が勤める会社に入社。
事務職で数年働いた後、どういう縁か父と結婚し、結婚を機に退職したときいている。
馴れ初めの話は聞いたことないし、聞く気もない。
母親は少し苦労人の人生らしく、学生時代は体の弱い両親に代わり祖父母の面倒を見るために、あまり友達と遊ぶ時間がなかったそうだ。
祖父母がなくなった後にも、あまり遊ぶことはなく、カラオケやゲームセンターには一度も行ったことがないと聞いたときは驚いてしまった。
そんな生い立ちからか、私が友達とどこかに行くときは詳細な行先を母親に伝え、そして実際に行った場所を細かく報告する必要がある。
万が一、行き先が事前にと異なっていた場合や、自身が好ましくないと思っている場所に行った時、何より、自分が認めない私の友達がいた時は、厳しく叱られた。
あの人は何が楽しいのだろうか。
友人関係は、母の基準で良い悪いが決められていた。
行きたい場所にも行けない、遊びたい相手とも遊べない。
それが日常だった小学生の頃は、本当に辛かった。
ただ高校に進学し、母親の態度が若干軟化した。
それは県内でもトップクラスの女子校に入学したからというあからさまな理由。
心底、気持ち悪いと思った。
子供のころは母親が世界で、全てだった。母親の価値観で物事を判断され、すべての行動が決まっていく。
何か説明を求めても、納得いく回答が得られることはなかった。
(なんで、○○ちゃんど遊ぶと怒るの?)
(100点じゃないとなんでダメなの。難しい問題あったんだよ…………)
幸い、自分が置かれている環境が少しおかしいと気がついたのは、たくさんの本のおかげだった。
母親も父親も、本を読んでいる姿は一度も見たことがない。
一方的に、私に本を読むということを強要するだけ。
最初はイヤイヤ読んでいたと思うが、本は多種多様な知識・教養を学ぶことも、多くの人の人生を追体験することもができる。
その楽しさに気が付いた後は、私の世界を大きく、大きく広げてくれた。
母親は、私が本さえ読んでいればよく、本の内容まで干渉してこなかったのは幸いだった。
まさか娘が、毒親について書かれた本まで熱心に読んでいたとは夢にも思わなかっただろう。
中学に上がる頃には、母親が満足する娘の姿が大体分かったため、それを踏み越えないよう、それだけに注意して過ごしていた。
また中学は複数の小学校から進学するため、生徒の人数が大きく増え、ここでも世の中には色々な人がいることを知り、部活も始まったことで母親から離れられる時間もかなり増えた。
部活にはあまり馴染んでいたとは言えなかったけど、私は母親から離れられる時間があることが嬉しくて、部活も苦痛ではなかった。
そして母親からの私の評価は、定期テストの結果という順位で明確に表され、それが全てだった。
この定期テストの結果は、母親に満足を与えるだけではなく、私の勉強に費やした努力を強烈に肯定してくれた。
順位という形で私の居場所を与えてくれ、今まで母親から否定され続けて崩壊寸前だった私の承認欲求を満たしてくれたことには救われたが、やはり手放しでは喜べず、複雑な気持ちが拭えなかった。
もちろん、これまで両親が相応のお金と時間を私にかけてくれたことは理解しているし、有形無形の形で私を支援してくれているということが分からない歳でもない。
ただそれを事実として理解しているだけで、いくら他人から非難されようとも少しも感謝はしていない。
本を沢山読むことで、我が家はどうやら一般的にはおかしい家であるということに気づき、出会う人が多くなったことで、様々な価値観をもつ人がいることもできた。
結果、私は世界の中心が母親ではないと知った。
歳を重ねることで世間一般では大人として定義されていても、変わらず自分自身の小さな世界に閉じこもり、外に目を向けない母親。
同時に私は、彼女とは一生分かり合えないとようやく理解した。
私と母親との距離はこの時に決定したと思う。
将来きちんと独立して、この家と離れて生きていくことが、私の目標であり夢となった瞬間だった。
高校に入学して、自分はさほど勉強ができる方ではないという事実を突きつけられても頑張れたのは、母親が納得するだけの県外の大学に合格することができれば、夢への第一歩として、堂々とこの家から出ることができるから。
あと数年なら頑張れる。
ガマンできる。
『頑張るのことは当たり前』、『頑張らなければ一生このまま』、『頑張らないのはバカだ』と自分に言い聞かせてやってきた。
それは間違いじゃなかったはず。
そして、何よりも私は母親のようにはならない。
自分の価値観に閉じこもって、それを他人に押し付けるような人間には絶対にならない。
そう信じてやってきた。
「ただ……私も同じだった。あの母親と」
何か達成したい目標のために頑張るのは自分のため。
少なくとも私が頑張るのは自分のためで、自分の周りの人間が頑張っていなくても、それはまったく関係がない。
それなのに私は、青井 日和という人間を、目に見える部分だけで頑張っていない人間と判断し、あまつさえダメな人間であるというレッテルを勝手に張った。
自分の価値観を押し付けていた。
(反面教師にすると決め、あれだけ嫌悪していた母親と、私も同じだ)
救われない。
自分自身が本当に嫌になった。
なぜこんなことになった………………。
私が入学したこの学校は、県内の各中学校から上位にいた人たちが集まってくるようなところだ。
私が必死に量をこなしてなんとか上位を維持していた勉強も、そういった努力が少なくて済む人がいるのは当たり前。
それは才能かもしれないし、効率的な方法を知っているからかもしれない。
素質がある人にも、さらなる高みを目指して頑張る人がいる。
そんな中で、私は以前と同じように頑張っても成果が伴わず、自分が感じている以上にストレスを抱えていたのかもしれない。
ただそんなことは、本当にくだらない言い訳だ。
自分が思う理想の自分になれないこと。
友達も少なく、頑張っても、頑張っても、それが結果で報われないという事実。
青井のことは、そういった劣等感が、無意識のうちに嫉妬となり、自分の価値観に合わない人間をダメな人間と定義し、レッテルを貼ることでストレスを解消していたこと以外の何ものでもなかった。
「最低じゃん」
しかも、それが自分の中だけで完結していたのならまだいい。
私は、あろうことか、人を、青井を傷つけるかたちで、醜い自己満足を得ていたのだから救いがない。
「本当に最低……」
何で私が青井のことが嫌いなのかようやく分かった。
青井は勉強もできるし、友達も多い。
運動も人並みにでき、常に誰かが周りにいる。
反面、表面上は何か頑張っている素振りもなく、常に受け身。
私はそれが許せなかったのだ。
『頑張らなくてもできる』
そう言われているようで、自分を完全に否定されているようで、我慢ならなかった。
何が「私は、青井 日和が嫌い」だ。
嫌いなのは、些細なことで嫉妬をしている自分だ。
『がんばっている自分は偉い』『がんばっている自分を認めてほしい』そんなくだらない承認欲求に支配されているだけだった。
(環境が変われば、私よりも、もっとできる人がいて、報われない努力もある。そんなこと当たり前じゃん)
今更、分かっても遅い。
ただ、こんな簡単なこともわからなかったのかと激しい自己嫌悪に襲われる。
私は、私には無い、青井 日和の生き方に、どうしようもなく惹かれたのだ。
「完全にただの嫉妬じゃん。子供じゃん」
言葉に出さずにはいられなかった。
その嫉妬を留めることができず、青井に対しての幼稚で最低な行動に繋がっていたのだ。
「どうしよう……」
状況が理解できたからといって、これまでの自分がしてきた過ちの数々が無かったことになるわけではない。
どろどろした重い記憶として頭の奥底からとめどなく湧き出てくる。
気がつけば、夜が明けていた。
帰宅し、疲れたからと言ってご飯も食べずに部屋に閉じこもったため、制服のままだ。
カーテンを閉めることも忘れて、ずっとベットの上でうずくまっていた。
立ちあがろうにも固まった体があちこち悲鳴をあげている。
青井から受けた質問への回答は、全くもって考えつかない。
(当たり前だ)
全ての原因は私にあったから。青井は関係ない。
何て応えたら良いか全くわからない。言いようがない。
「ごめん。実はまったくあなたのことが嫌いじゃなかった。許して」
私だったら絶対に許さない。
「ごめん。実は、自分の中で整理できない問題があって、それであなたに八つ当たりしてた。許して」
私だったら、絶対に許さない。それが自分に何の関係があるのか。そんなことで、自分は今まで嫌な思いをしていたのかと激しく相手を憎悪するだろう。
謝ることは当たり前だけど、今、彼女は謝罪を要求しているのではない、私に自分のことが嫌いかどうかを聞いてきたのだ。だから私は、まずそれに答えなければならない。回答は、嫌いか嫌いではないかの二択。
彼女に対する羨望から生じる嫉妬心は、まだ、ある。ただ、そんな幼稚なことで嫌いと言っていたなんてどうしようもない。
悩んでも答えはでない。答えが出なければ青井には会えない。学校には行けない。
私は、私の意思で、学校に行くのをやめた。……逃げた。
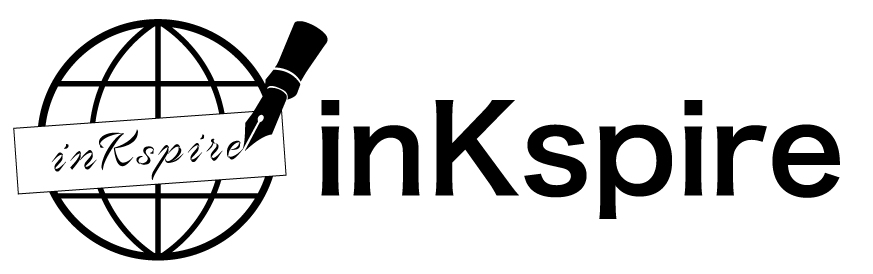






コメント